死亡時画像診断(Ai)とは?

死亡時画像診断(Ai、AutopsyImaging)は、遺体を対象にCTやMRIなどの画像診断技術を用いて死因を究明する手法です。
日本では「死亡時画像診断」として知られ、遺体を傷つけることなく、非侵襲的に内部の状態を確認できるため、近年注目されています。
剖検(病理解剖)と死亡時画像診断について
剖検と死亡時画像診断は、死因究明において重要な役割を果たしています。それぞれの方法には特有の利点と限界があります。
1:死亡時画像診断の目的
死亡時画像診断の目的は、死因の明確化であり、剖検の同意が取れない状況でも、迅速に施行することが出来ることが多く、死因を客観的に究明することが可能です。
2:剖検(病理解剖)について
剖検は、遺体を解剖して内部の状態を直接確認する伝統的な手法です。病気の進行状況や死因を詳細に分析が可能です。
しかし、御遺体に傷をつけることになるため、遺族の承諾が必要であり、心理的抵抗により、ご遺族の同意が得られないこともあります。
死因究明において、剖検は、最も詳細で正確な方法とされています。剖検では、臓器を直接観察し、肉眼で確認できる異常を詳細に調べることができます。組織学的検査により、細胞レベルでの変化を捉えることができ、微細な病変も発見可能です。また、様々な検査(薬毒物検査、DNA分析など)を組み合わせて、より包括的な死因分析が可能です。
しかし、日本では年間約20万の死因不明遺体があるにもかかわらず、法医学者による解剖が行われているのはわずか1割程度です。これは、90%近い解剖率を持つ諸外国と比較して極めて低い数字です。日本における低い剖検率の要因として、臨床医の剖検に対する意識の低さ、遺族の同意取得の困難さ、監察医制度の地域格差など制度上の課題、法医学者の不足、剖検費用の問題(1体あたり約25万円と試算)などがあります。
3:死亡時画像診断による死因推測の精度
■死因推測の精度
死亡時画像診断による死因推測の精度は、非外傷性死因でおおよそ30%程度とされています。
これは、体表検査のみの場合と比較すると高い精度ですが、解剖には及びません。
■死亡時画像診断の精度に影響する要因
使用する画像診断機器:主にCTが使用されますが、MRIを併用することで精度が向上します。
死因の種類:外傷性死因は8割以上、非外傷性死因は3割前後を診断できるとされています。
専門家の読影:画像診断の専門家による読影が重要です。
MRIの活用:CTでは診断が難しい虚血心筋、肺動脈血栓塞栓、頚髄損傷などをMRIで診断することで、死因確定率の向上が期待されています。
死亡時画像診断の利点
■非侵襲性
遺体を傷つけない:死後画像診断は非侵襲的であり、遺体を解剖する必要がありません。これにより、遺族の心理的負担が軽減され、同意を得やすくなります。
■迅速性と効率性
迅速な検査:CTスキャンなどの画像診断は短時間で実施可能であり、死因の推測や確定にかかる時間を大幅に短縮できます。例えば、CT検査は約10分で完了し、迅速な死因究明が可能です。
■全身のスクリーニング(広範囲の評価)
画像診断では全身を一度にスクリーニングできるため、特定の部位のみを調べる剖検とは異なり、見逃しが少なくなります。これにより、外傷や出血性疾患などの診断が容易になります。
■心理的な施行のしやすさ
御遺体に傷をつけることが無いため、御遺族の心理的な抵抗で剖検が難しい場合にも適した手法です。
■費用対効果と利用可能性
剖検(病理解剖)の場合、1体あたり約25万円かかるのに対し、死亡時画像診断では、約5万円~と低コストで実施できます。
■容易に検査が出来る環境
日本は世界で最も多くのCT装置が設置されており、比較的容易に検査を行うことができます。
これらの利点から、死後画像診断は死因究明において重要な手法として位置づけられています。ただし、一部の疾患については依然として剖検が必要な場合もあるため、両者を組み合わせて使用することが推奨されています。
死亡時画像診断が剖検より有効な状況
CTによる死後画像診断は、ガス塞栓症、緊張性気胸、肺病変など剖検で診断難しい病変が診断出来ることもあります。また、銃撃や刃物による損傷の際に、その損傷の経路をわかりやすく視覚化することは、剖検より優れていることがあります。剖検では難しい体腔液の評価も、死後画像であれば正確に推定できます。また、骨折や臓器損傷などの外傷を明確に判断することができます。特に、交通事故や暴力による外傷の評価において有効です。
児童虐待が疑われる場合の有用性
非侵襲的な検査である死亡時画像診断はCTやMRIを使用して遺体を非侵襲的に検査するため、遺体を損傷することなく内部の状態を確認できます。これにより、骨折や出血などの虐待の物理的証拠を迅速に発見することが可能です。
■迅速な死因究明と心理的負担軽減
児童虐待が疑われるケースでは、迅速な対応が求められます。死後画像診断は短時間で結果を得ることができるため、死因究明を迅速に行う手段として有効です。特に心肺停止状態で緊急搬送された場合など、即座に死因を特定する必要がある場面で役立ちます。 また、解剖に比べて身体を傷つけないため、遺族の同意を得やすく、心理的負担も軽減されます。これにより、死因究明に対する遺族の協力が得られやすくなります。
■虐待の証拠収集
死亡時画像診断は虐待の物理的証拠を収集する上で重要な役割を果たします。例えば、頭部外傷や肋骨骨折など、虐待に関連する損傷を詳細に確認することができます。 これらの利点から、死亡時画像診断は児童虐待が疑われる場合において、迅速かつ非侵襲的な死因究明手段として非常に有効です。
まとめ
死亡時画像診断は、死因究明において重要な役割を果たす手法として、日本国内で普及しつつあります。特に非侵襲的であることから遺族の理解を得やすく、迅速な診断が可能である点で優れています。
■専門家による読影の重要性
死亡時画像診断では、専門的な知識と経験を有する放射線科医や法医学者が画像を読影し、死因究明に必要な情報を提供します。これにより、伝統的な剖検では見逃される可能性のある微細な異常も検出可能です。
■iMedicalの死亡時画像診断、遠隔画像診断支援サービス
iMedicalの死亡時画像診断、遠隔画像診断支援サービスでは、全国的にも数少ない法医学の実務に精通した放射線科診断専門医による死後画像診断の読影を依頼することが可能です。
(監修:高櫻 竜太郎)
関連記事:遠隔画像診断支援サービスの導入方法は?メリット・費用なども解説
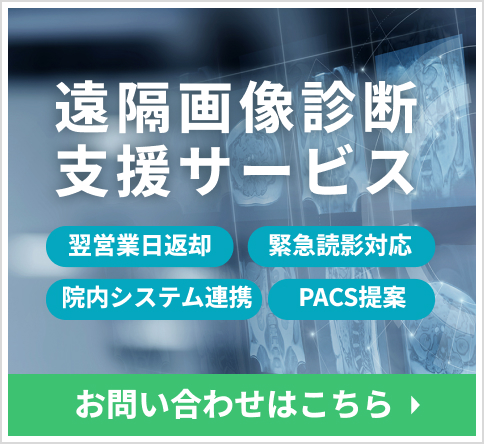

.png)
.png)