クリニックの人手不足の原因は?影響や対策を解説

近年、クリニックにおける人手不足が深刻化しており、診療の現場にさまざまな影響を及ぼしています。
特に、医師や看護師をはじめとする医療従事者の負担増加は、診療の質の低下や診療時間の短縮につながりかねず、最終的には患者満足度の低下やクリニック経営の不安定化を招く要因にもなり得ます。
本記事では、クリニックの人手不足が与える影響、原因、実効性のある対策について詳しく解説します。
人手不足がクリニックに与える影響
人手不足がクリニックに与える影響について詳しく見ていきましょう。
患者対応の遅延による満足度低下
クリニックの人手不足が深刻化すると、受付や診療の待ち時間が長くなり、患者満足度の低下につながります。
特に初診患者は長時間の待機を強いられることで、次回以降の受診を躊躇する可能性が高まります。
医療従事者の負担増加と離職リスク
人手不足により、一人ひとりの医療従事者にかかる業務負担が増大します。
特に医師や看護師は、診療時間の延長や業務の多様化によって、疲労や精神的ストレスが増加・蓄積し、離職のリスクが高まります。
医療サービスの質の低下
十分なスタッフが確保できていない状況では、患者ごとの診療時間を十分に確保することが難しくなります。
医師は短時間で多くの患者を診察せざるを得ず、病状の聞き取りや診察の精度が低下するリスクが生じます。
診療時間の制限による患者受け入れの減少
医療従事者の不足は、診療時間の短縮や診療枠の削減を招く要因です。
例えば、夜間診療や土日診療を行っていたクリニックが、スタッフ不足を理由に診療時間を短縮すると、受診の減少につながります。
経営面での収益低下
人手不足が継続すると、患者対応の遅れや診療枠の減少によって、クリニックの収益に影響が及びます。
また、医療従事者の負担を軽減するために一時的に派遣スタッフを活用すると、人件費の増加がクリニックの財務状況を圧迫する要因となりかねません。
クリニックの人手不足の原因
クリニックの人手不足の原因は次のとおりです。
医療従事者の離職率の高さ
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果」によると、医療・福祉分野の離職者数は2022年(令和4年)で約1,210,000人、2023年(令和5年)で約1,157,100人と、約52,900人減少(約4%減)しました。
一方、入職者数は約1,138,100人(2022年)から約1,266,500人(2023年)へと増加し、離職者数の減少に対して入職者数の増加が見られた結果となっています。
ただし、この前年である2021年(令和3年)のデータを見ると、離職者数約1,056,400人、入職者数約1,120,800人と、入職者数増加の傾向は続くものの2022年にかけて離職者数の大幅な増加が見られており、離職者数の減少が今後も続くとは限りません。
高齢化社会による医療需要の増加
政府の推計によると、2025年には団塊の世代が全員75歳以上となり、後期高齢者が全人口の約18%を占めるようになります。
高齢になるほどに疾患の罹患率が上昇するため、定期的な通院や医療ケアが必要になることで、医療機関の負担はさらに大きくなるでしょう。
2040年には、65歳以上の人口が全人口の約35%を占めるようになり、2070年には総人口が9,000万人を下回り、高齢化率は39%に達する見込みです。
人手不足に対する具体的な対策

クリニックの人手不足に対しては、次のような対策があります。
働きやすい職場環境の整備
人手不足を根本的に解決するためには、医療従事者が働きやすい職場環境を整備し、定着率を向上させることが不可欠です。
まず、スタッフの労働時間を適切に管理し、過度な負担がかからないように調整することが求められます。例えば、診療スケジュールの最適化やシフト制の導入があります。
次に、職場の人間関係やコミュニケーションを円滑にするための仕組みづくりも重要です。例えば、定期的なミーティングを設け、スタッフの意見を聞く機会を増やすことで、職場の課題を早期に把握し、改善策を講じることができます。
また、新人スタッフの教育制度を充実させることで、業務への不安が解消されやすくなり、離職率の低下につながります。
さらに、福利厚生の充実も職場環境の改善において重要です。例えば、育児支援制度や時短勤務制度の導入により、ライフステージに応じた働き方を選択できるようにする方法があります。また、定期的なリフレッシュ休暇や、外部研修への参加支援などを取り入れて、モチベーションの維持・向上を図ることも効果的です。
IT化と業務効率化の導入
人手不足を補うためには、限られた人員で最大限の業務効率を実現する仕組みが不可欠です。診療や事務作業のIT化を進め、業務の自動化・効率化を進めましょう。
例えば、電子カルテやオンライン問診システムを導入することで、医師や看護師の業務負担を軽減できます。
IT化を進める際は、導入コストと運用コストのバランスを考慮し、長期的に効果を見込めるシステムを選定することが重要です。
遠隔画像診断支援サービスの活用
画像診断を必要とするケースでは、専門医の不足や読影にかかる負担が大きな課題となっています。こうした課題を解決する手段として、遠隔画像診断支援サービスの活用がおすすめです。
遠隔画像診断支援サービスは、院内で撮影したレントゲンやCT、MRIなどの画像を、外部の読影医が診断し、レポートを提供するサービスです。
導入にあたっては、信頼性の高い読影医ネットワークを持つサービスを選定することが重要です。また、データのセキュリティ対策や、診療フローへの適合性を事前に検討し、スムーズに運用できる体制を整えることが求められます。
遠隔画像診断支援サービスの導入方法やメリット、費用について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:遠隔画像診断支援サービスの導入方法は?メリット・費用なども解説
遠隔画像診断支援サービスの導入効果
遠隔画像診断支援サービスの導入効果について、さらに詳しく見ていきましょう。
専門医不足の解消
クリニックにおける診断業務の中でも、画像診断は特に専門性が求められる領域です。しかし、放射線科専門医をはじめとする画像診断のエキスパートが常駐するクリニックは限られ、読影の負担が医師に集中しやすいことが課題となっています。
遠隔画像診断支援サービスを導入することで、院内に専門医が不在でも、外部の放射線科専門医が読影を担当し、迅速かつ正確な診断結果を提供することが可能になります。
また、都市部に比べて専門医の数が限られている地方では、放射線科専門医が常勤で勤務することが難しく、読影の質やスピードに影響が出るケースがよく見られます。しかし、遠隔画像診断支援サービスを活用すれば、全国の専門医ネットワークを生かし、24時間体制で 迅速な画像診断を実現することが可能です(サービス内容によって異なります)。
診断精度向上
遠隔画像診断支援サービスの導入によって、診断精度の向上が可能 です。読影には高度な専門知識が求められるため、一般臨床医が自己判断で画像診断を行う場合と比べ、専門医による読影は診断精度が高いです。
遠隔画像診断サービスでは専門医が細かい所見までチェックし、適切な診断へとつなげます。
特に、がんや血管疾患などのケースでは、命に関わる決断を迫られることからセカンドオピニオンを求める患者も多く、専門医の判断が求められる場面が増えています。
遠隔診断を活用することで、クリニック内での診断だけに頼らず、外部の専門家の知見を生かした質の高い診療を提供することが可能になります。
まとめ
クリニックの人手不足は、医療従事者の負担増加、診療の質の低下、診療枠の縮小、経営への影響など、さまざまな問題を引き起こします。
この問題を解決するためには、遠隔画像診断支援サービスの活用による専門医不足の解消、ITの導入による業務効率化、医療従事者の働きやすい環境整備による定着率向上といった具体的な対策が不可欠です。
iMedicalの遠隔画像診断支援サービスは、100名以上の放射線科診断専門医による質の高い診断を提供しています。緊急時には2時間以内での返却も可能です。
遠隔画像診断支援サービスの詳細については、お気軽にご相談ください。
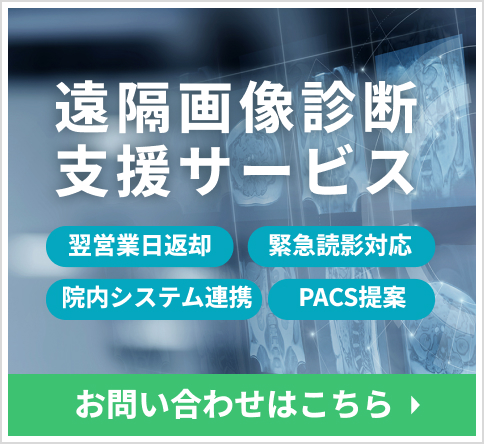

.png)
.png)