遠隔医療のメリットとは?種類やデメリットも解説

近年、医療現場において急速に注目を集めているのが「遠隔医療」です。インターネットや通信機器を活用することで、患者と医師が離れた場所にいながら診療が可能となり、これまで通院が困難だった人々にとって大きな希望となっています。
本記事では、遠隔医療の基本的な仕組みや主な種類、オンライン診療との違いを分かりやすく整理し、実際に利用する上でのメリット・デメリットについても詳しく解説します。
遠隔医療とは
遠隔医療とは、情報通信機器を活用して、医師と患者が物理的に離れた場所にいながら診療を行う医療の形態を指します。近年、通院が困難な高齢者や慢性疾患の患者、離島・へき地に住む人々への診療手段として拡大しつつあります。
厚生労働省の見解では、遠隔医療は対面診療の代替ではなく補完的な手段とされており、患者の状態や診療内容によっては原則として対面診療が優先されます。ただし、患者から得られる情報が医師法に定められた「診察」として成立する水準に達していれば、遠隔医療も認められています。
遠隔医療の主な種類
遠隔医療にはさまざまな形態があります。ここでは、遠隔医療の主な種類について詳しく見ていきましょう。
オンライン診療
オンライン診療は、インターネットを活用して、患者が自宅や職場などから医師の診察や服薬指導を受けられる診療形式です。スマートフォンやタブレットを使用し、映像と音声を通じてリアルタイムにやり取りを行うことで、遠隔でも医療サービスを受けることが可能です。
通院に伴う移動時間や待ち時間を削減できるため、患者の負担軽減や医療アクセスの向上につながります。花粉症、高血圧、軽度の皮膚炎など、緊急性が比較的少なく対面での診察を必ずしも必要としないケースでは、オンライン診療が選択肢となります。
一方で、オンライン診療には限界もあります。画面越しでは視診や問診が中心となるため、触診や聴診といった診察行為が行えず、診断に必要な情報が不足するおそれがあります。そのため、緊急性が高い症状や病状の変化が激しい場合には不向きであり、医師の判断によっては対面診療への切り替えが必要です。
電話相談
電話相談は、患者が医師や看護師などの医療従事者に対して電話を通じて健康や症状に関する相談を行う仕組みです。遠隔医療の中でも比較的導入のハードルが低く、災害時や感染症流行時など、対面診療が困難な状況において幅広く活用されてきました。
主な役割は、医療機関を受診すべきかどうかの判断や、現在の症状への対処法、薬の服用に関するアドバイスなどを迅速に提供することにあります。実際の診断行為や処方は行えませんが、患者の不安を軽減し、適切な医療機関への案内につなげる点で重要な役割を担っています。
リモートモニタリング
リモートモニタリングは、血圧計や心電計、血糖測定器などの検査機器を用いて患者のバイタルデータを取得し、その情報をインターネット経由で医療機関に送信・共有する仕組みです。医師や看護師は、送られてきたデータをもとに患者の状態を把握し、必要に応じて診療や生活指導を行います。
高血圧や糖尿病、心不全などの慢性疾患においては、日々の変化を見逃さずに管理することが重要とされており、リモートモニタリングは早期の悪化予防や入院リスクの低減に貢献します。
遠隔読影
遠隔読影は、医療機関で撮影したCTやMRIなどの医用画像を、インターネット経由で外部の読影医に送信し、専門医による診断レポートを受け取る仕組みです。放射線診断専門医が常勤していない医療機関や、夜間・休日も画像診断体制を維持したい医療機関にとって、重要な選択肢となっています。
遠隔読影の導入により、医師不足が深刻な地方や離島でも、質の高い画像診断を継続的に提供することが可能になります。また、外部の読影医が24時間体制で対応している場合は、急患や夜間の緊急検査にも柔軟に対応でき、医療現場の安心感と業務効率の向上にもつながります。
遠隔医療のメリットとデメリット

遠隔医療は、患者・医療者の双方にとって利便性や効率性をもたらす一方で、技術的・制度的な課題も存在します。
ここでは、遠隔医療の主なメリットとデメリットについて解説します。
メリット
まずは、遠隔医療のメリットについて見ていきましょう。
医療資源の有効活用
遠隔医療は、医師や専門医の偏在といった地域格差の解消に貢献します。特に地方や離島などでは、診療科の選択肢が限られていたり、専門医の常駐が困難であったりするケースも少なくありません。遠隔医療を活用することで、都市部にいる専門医が画像診断や問診を通じて診療に関与できるようになり、医療資源の分配をより合理的に行えるようになります。
時間・場所の制約を超えた医療提供
遠隔医療の導入によって、診療を受けるために移動する必要がなくなり、患者は自宅や職場など、どこからでも医療サービスを受けることができます。これは、通院に時間を割くことが難しいビジネスパーソンや、育児や介護で外出が困難な方、交通の便が悪い地域に暮らす方にとって、大きなメリットです。
また、診療予約の幅が広がることで、夜間や休日にも対応しやすくなり、生活スタイルに合わせた柔軟な医療利用が可能となります。医師にとっても、診療時間を分散することで一人ひとりに丁寧な対応がしやすくなるため、患者満足度の向上にもつながります。
感染症リスクの軽減
医療機関は多くの人が出入りする場所であり、風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルスといった感染症が流行する時期には、待合室での二次感染リスクが高まります。
遠隔医療を導入することで、こうした人が集まる空間を避けつつ診療が受けられるため、患者本人だけでなくほかの来院者や医療スタッフにとっても感染防止の効果があります。
デメリット・課題
遠隔医療はさまざまなメリットを持つ一方で、現時点ではいくつかの課題や懸念点が残されており、医療現場や社会全体での慎重な対応が求められます。遠隔医療のデメリットと課題について詳しく見ていきましょう。
通信インフラ・セキュリティの整備
遠隔医療を円滑に実施するためには、安定したインターネット接続環境とセキュリティ対策の両方が不可欠です。通信が不安定で映像や音声が途切れると、正確な診断が困難になり、誤診や情報の行き違いにつながるおそれがあります。
また、遠隔医療はインターネットを通じて個人情報や医療データをやり取りするため、通信の暗号化や不正アクセス防止など、高度なセキュリティ対策が求められます。もし医療情報が漏えいすれば、患者の信頼を損なうだけでなく、医療機関としての社会的信用にも影響するため、インフラと情報管理体制の強化が欠かせません。
患者のITリテラシー格差
遠隔医療を活用するには、スマートフォンやタブレット、パソコンなどの端末操作に一定の理解が必要です。しかし、高齢者やITに不慣れな方にとっては、アプリのダウンロード、ビデオ通話の設定、問診票の入力などが負担になることもあり、診療の機会そのものを逃してしまうケースもあります。
さらに、視覚・聴覚障がいを持つ方や日本語が母語でない外国人にとって、遠隔での操作やコミュニケーションは一層の困難を伴う可能性があります。このようなITリテラシーの格差を埋めるためには、端末の操作サポートや、医療機関による事前のフォロー体制、ユーザーインターフェースの簡素化などが必要です。
プライバシー保護と個人情報管理
遠隔医療では、診察内容や処方情報、疾患歴など、極めてセンシティブな個人情報を電子的に取り扱う必要があります。したがって、これらの情報をどのように保存するのか、誰がアクセスできるのかという管理体制の明確化が極めて重要です。
また、通信手段として利用されるプラットフォームが、医療情報の取り扱いに準拠しているかを確認する必要もあり、医療機関には慎重なベンダー選定とセキュリティ基準の遵守が求められます。
まとめ
遠隔医療は、医療資源の有効活用や患者の通院負担軽減、感染症対策といった観点から、今後さらに注目される分野です。中でも遠隔読影は、放射線科医の不足や読影精度への不安、業務効率の課題を抱える医療現場にとって、前向きに検討したい対策といえます。
iMedicalの遠隔画像診断支援サービスは、こうした現場のニーズに応えるために、100名以上の放射線科診断専門医と連携し、CTやMRIをはじめとする多様なモダリティに対応しています。PACS連携やレポートの自動取り込みなど、スムーズな導入と運用を実現する仕組みも整っています。
読影体制の見直しや業務効率の向上、診断精度の向上をお考えの際は、iMedicalまでぜひご相談ください。
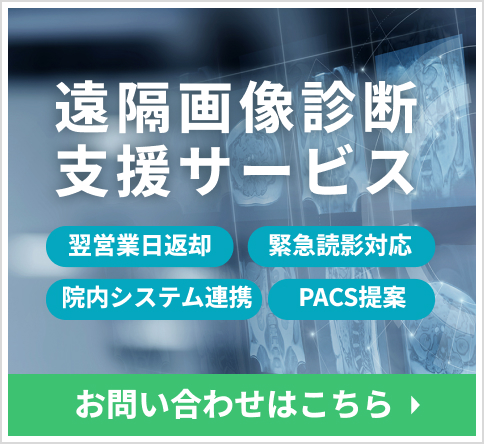

.png)
.png)