日本の医療現場は長年、医師の長時間労働によって支えられてきましたが、この状況を改善し、持続可能な医療体制を構築することが急務となっています。「医師の働き方改革」は、医師が健康に働き続けることができる環境を整えると同時に、患者に対して質の高い安全な医療を提供し続けるための重要な取り組みです。
2024年4月には、医師の働き方改革に関わる制度のうち、医師の残業時間に上限を設ける制度や勤務間インターバルに関する制度が開始されました。本記事では、医師の働き方改革の目的と、その実現に向けたポイントを詳しく解説します。
医師の働き方改革とは
2024年4月より、「医師の働き方改革」に伴い、医療機関における労働時間の上限規制が施行されました。一般の医師には年間960時間の時間外労働の上限が設けられ、地域医療や救急医療などの特別な医療機関に従事する医師には、年間1,860時間までの上限が適用されることが決定しています。
これに加え、医師の健康を守るため、面接指導や連続勤務時間の制限、勤務間インターバル規制といった健康確保措置が義務化されました。
医師の職場の現状と働き方改革の目的
日本の医療現場は、医師の長時間労働によって支えられてきましたが、その一方で医師の負担は限界に達しつつあります。医師が健康に働き続けられる環境を整備し、質の高い医療を持続的に提供するための改革が「医師の働き方改革」です。
医師の働き方改革の目的は、患者に対して安心して医療を提供し続けられる体制を築くことです。これを達成するために、下記の目標が掲げられています。
医師の長時間労働の是正
厚生労働省によると、現状では病院に常勤する勤務医の約4割が年間960時間以上、さらに約1割が年間1,860時間以上の時間外・休日労働をしています。特に、救急医療、産婦人科、外科、そして若手医師において長時間労働の傾向が顕著です。
長時間労働は医師の健康に重大な影響を及ぼし、ひいては医療の質を低下させる要因となります。このため、医師の長時間労働の是正が急務であり、働き方改革では医師の健康を守るための労働時間の上限規制が導入されています。
各医療従事者が自身の能力を生かした対応の実現
各医療従事者が専門知識や能力を最大限に生かし、能動的に対応できるようにすることも目標の一つです。
例えば、看護師や薬剤師などの医療従事者が、医師の業務の一部を分担する「タスクシフティング」を推進することで、医師の負担が軽減し、医療の質を高めることが期待されています。医師は本来の診療業務に集中でき、患者に対してより質の高い医療を提供できるようになります。
医師の働き方改革に伴う時間外労働の上限
医師の働き方改革において、医師の残業時間に上限を設ける制度については、下記のように定められています。
| 水準 | 年の上限時間 |
| A水準(すべての勤務医に対して原則的に適用) | 960時間 |
| 連携B水準(地域医療の確保を目的とし、副業・兼業として派遣される場合に適用) | 1,860時間(各院では960時間) |
| B水準(地域医療の確保を目的とし、自院内で長時間労働が必要な場合に適用) | 1,860時間 |
| C-1水準(臨床研修医/専門医の研修を目的として、長時間労働が必要な場合に適用) | 1,860時間 |
| C-2水準(専門医を卒業した医師の技能研修を目的として長時間労働が必要な場合) | 1,860時間 |
出典:厚生労働省「医師の働き方改革~患者さんと医師の未来のために~」
上記を満たした上で、月の残業時間は100時間未満とする必要があります。ただし、面接指導を実施することで、100時間以上の残業が可能になる例外もあることに注意が必要です。
どの水準に当てはまるかを自己判断するのではなく、医療機関が都道府県に指定申請し、認められる必要があります。また、水準は医療機関単位ではなく医師単位で定められます。
医師の働き方改革に際して医療機関が取るべき対応

医師の働き方改革を実現するためには、医師の健康を守りつつ、質の高い医療を継続的に提供できる労働環境を整える必要があります。医療機関が取るべき主要な対応策について、詳しく見ていきましょう。
労働時間管理の適正化
労働時間管理の適正化は、医師の長時間労働を是正し、労働環境を改善するための基盤となります。労働時間管理の適正化には、例えば勤務時間モニタリングシステムの導入が有用です。機能の一例としては、医師一人ひとりの勤務時間をリアルタイムで追跡し、残業時間の上限を超える恐れがある場合、医師や管理者に自動的にアラートが送られるというものがあります。
医療機関が注意すべきは残業時間だけではありません。2024年4月からは勤務間インターバルの確保も義務付けられています。勤務間インターバルとは、始業から一定時間内に一定以上の連続した休息時間を与えることです。
日勤および宿日直許可のある宿日直を行う際は、24時間以内に9時間の連続した休憩を確保する必要があります。また、宿日直の許可がない場合は、始業から46時間以内に18時間の連続した休憩を確保する必要があります。
タスクシフティング・タスクシェアリングの推進
タスクシフティング・タスクシェアリングは、これまで特定の職種が担っていた業務を他の職種にシフト(移管)したり、シェア(共有化)したりすることで、医療現場の効率化を図る取り組みです。専門職同士が自身の専門性を生かし、各職種が協力しながらより能動的に業務に取り組むことが可能になります。
主な目的は、医療従事者の業務負担を最適化し、全体として医療の質を維持または向上させることにあります。例えば、看護師が医師の業務の一部を引き受けることで、医師はより高度な医療行為に集中することができ、全体として医療現場が効率化されます。
さらに、看護師だけでなく、医師以外の職種と看護師の間での業務分担も重要です。例えば、看護補助者や他の医療専門職との協働により、看護師がより専門的な業務に集中できるようにすることが、全体の医療の質を向上させるための一助となります。
ICTの活用
ICT(情報通信技術)の活用は、医療現場において業務効率化を図り、医師の労働負担を軽減するための鍵となります。診療の質を向上させると同時に、医療提供体制の持続可能性を高めることができます。医師の働き方改革に役立つICTについて、詳しく見ていきましょう。
▼遠隔画像診断支援サービス
遠隔画像診断支援サービスは、医療機関で撮影したCTやMRIなどの画像データを、インターネットを通じて外部の読影医に送信し、画像診断の結果が記された診断レポートを返却するサービスです。
医師が不足している地方の医療機関や放射線科専門医が不在の医療機関においても、質の高い診断が可能となり、医師の負担も軽減されます。特に、働き方改革において医師の労働時間を削減しつつ、高度な医療を維持したい場合に効果的です。
遠隔画像診断支援サービスの費用について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

遠隔画像診断支援サービスの導入方法は?メリット・費用なども解説
▼電子カルテシステム
電子カルテシステムは、デジタル化したカルテを一元管理するツールです。紙のカルテを廃止し、患者情報をデジタルで一元管理することで、複数の医療従事者が同時にカルテの閲覧・入力が可能となり、生産性の向上が期待できます。
こうしたシステムの導入とあわせて医師事務作業補助者を配置する等、タスクシフティング・タスクシェアリングを推進することにより、医師はカルテ入力業務にかける時間を削減でき、診療に集中できるようになります。
▼Web問診システム
Web問診システムは、患者が事前にスマートフォンやパソコンを使って問診票をオンラインで提出することで、医師が事前に患者の症状や病歴を把握できる仕組みです。これにより、外来の待ち時間が短縮され、診療を効率的に進められます。
勤務態勢の見直し
医師の働き方改革を進めるためには、勤務態勢の見直しが不可欠です。これまで、多くの医療機関では、特に夜間や休日のシフトが過度に医師に依存している状況が見受けられました。例えば、救急科や産婦人科などの医師は、24時間体制で緊急対応が必要とされるため、連続勤務や長時間労働が当たり前になっていました。しかし、これでは医師の健康が損なわれるだけでなく、医療の質も低下しかねません。
働き方改革の一環として、シフト勤務を見直し、労働時間を削減することで、医師の負担軽減を図ることが大切です。
女性医師の支援
女性医師の活躍を推進することも、医師の働き方改革の重要な課題です。女性医師は、出産や育児といったライフイベントを迎える中で、キャリアの継続が難しいと感じることが多く、特に夜勤や長時間労働が大きな障壁となっています。
女性医師が家庭と仕事を両立しやすくなるように、育児中の女性医師に対して、夜勤免除や短時間勤務を選択できる制度を導入することも大切です。
他にも、女性医師同士が互いに支援し合うコミュニティの設立や、キャリア相談を行う専門のカウンセラーを配置するなど、さまざまな取り組み方があります。
まとめ
医師の働き方改革は、医療現場における医師の労働環境を改善し、質の高い医療の提供を持続可能にするための重要な取り組みです。労働環境を見直す際は、ICTを活用して時間を捻出することも検討しましょう。
iMedicalの遠隔画像診断支援サービスは、読影医の不足や専門分野の不安など、医療機関が抱える課題を解決します。
iMedicalが選ばれる理由として、以下の点が挙げられます。
・100名以上の放射線科診断専門医と連携し、常に質の高い診断レポートを提供
・PACSやレポートシステムとの連携が可能で、業務効率を大幅に向上
・各分野に特化した読影医がCT/MRのレポートを迅速に返却
・緊急時には2時間以内の対応も可能
遠隔画像診断支援サービスの導入を検討される際は、お気軽にご相談ください。

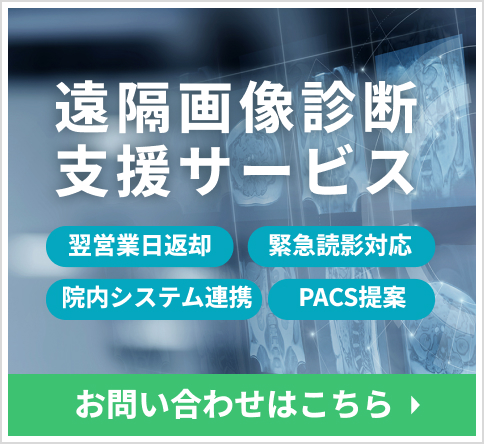

.png)
.png)