健診に遠隔読影は利用できる?メリット・注意点を解説

健康診断の需要が増加する中、読影医の不足や季節ごとの需要変動、迅速な結果報告の対応など、健診機関が抱える課題も多様化しています。こうした背景から、地域に専門医がいなくても質の高い診断を提供できる遠隔読影が注目されています。
本記事では、健診で遠隔読影を利用するメリットや、注意すべきポイントなどについて詳しく解説します。
健診における読影のよくある課題
健診における読影には、次のような課題があります。
読影医不足
読影医の業務では高い専門性と責任が求められるため、検査結果を適切に解釈するには高度な知識と豊富な経験が不可欠です。近年、健康志向の高まりと医療技術の進歩により、健康診断の需要が増加しており、読影医への需要も増大しています。
しかし、読影医の高齢化が進む中で、経験豊富な医師が引退した後の後任を確保するのは容易ではありません。
このような人材不足により、現職の読影医に業務が集中しているのが現状です。
需要の変動に応じた人材確保が難しい
健診は、企業や学校が定期的な健康管理の一環として行うため、年間を通じて需要があります。特に4月から6月にかけては、新入社員や学生を対象とした健診が集中するため、医療機関や検診センターが繁忙期を迎えます。
企業や学校からの健診予約が急増し、予約が取りにくくなることが一般的です。また、4月から6月に予約が取れなかった企業が9月から11月に予約を入れるため、この期間も繁忙期と言えるでしょう。
一方で、1月から3月は年度や学期の切り替えを控える時期であり、健診の需要は落ち着く傾向にあります。このように、年間を通じて健診には繁忙期と閑散期が存在し、その変動に応じた人材確保が難しいという課題が生じています。
結果報告書作成に時間がかかる
健診機関にとって、健診結果報告書をいかに早く受診者に届けるかは重要な課題の1つです。結果報告書の平均的な納期は地域差がありますが、おおよそ4週間程度で、早いところでは2週間以内です。
しかし、結果報告書作成の迅速化には課題があります。中でも大きな課題として、胸部X線や胃透視をはじめ、超音波、眼底、内視鏡、胸部CT、脳MRIなど多様な検査に対応できる専門医が在籍していないことが挙げられます。
それぞれの検査分野に精通した医師を確保するのが難しく、報告書作成期間を長引かせる一因となっています。
健診に遠隔読影を利用するメリット
健診に遠隔読影を利用することには、次のメリットがあります。
読影医不足を解消できる
遠隔読影を活用することで、医師が不足している地域でも専門的な読影を行うことが可能になります。
日本では医師の地域偏在が課題となっており、読影医が不足している地方の医療機関が多々みられます。遠隔読影を導入すれば、医師がいなくても専門性の高い読影ができます。
需要変動に伴う人材確保の負担が減る
遠隔読影を利用することで、健診需要の変動に柔軟に対応できます。
学生健診や企業の入社後健診が重なる繁忙期には、院内の医師のみで全ての読影を対応するのが難しい場面もありますが、遠隔読影を利用することで迅速かつ精度の高い対応が可能になります。
一方で、閑散期には健診需要が落ち着くため、院内医師だけで業務を回せるケースが多いでしょう。繁忙期に合わせて医師を雇用すると、閑散期に余計な人件費が発生しますが、遠隔読影を利用すればコストを最適化できます。
緊急時のバックアップとして機能する
読影医が在籍している場合でも、遠隔読影を緊急時のバックアップとして利用できます。
たとえば、急な読影依頼が重なった場合や、予期せぬ理由で読影医が不在となった場合でも、遠隔読影を利用すれば即座に代替の読影対応が可能になります。
健診に遠隔読影を利用する際の注意点
健診に遠隔読影を利用する際は、次の注意点を押さえましょう。
セキュリティ対策が不十分な場合がある
遠隔読影では、検査データの送信や保存においてセキュリティリスクが発生する可能性があります。受診者の診断情報や検査結果への不正アクセスを許してしまうと、第三者に情報が漏洩し、医療機関の信頼性を大きく損ねることになりかねません。
医療機関や遠隔画像診断支援サービスの提供者は、暗号化によるデータ保護やアクセス制御など、強固なセキュリティ対策を導入し、安全な情報管理を徹底することが重要です。
コストがかかる
医療機関や遠隔画像診断支援サービスの提供者によって、月額基本料金や初期導入費用、オプション費用などが異なります。
初期導入費用は、院内で使用しているPCやシステムが適合しないために買い換えが必要になったり、設置場所の関係で配線工事を行ったりした場合は高くなります。
また、毎月のランニングコスト(基本料金)は長期的にかかるため、年間コストを見積もり、現実的な予算計画を立てましょう。
なお、遠隔画像診断支援サービスの導入費用について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

関連記事:遠隔画像診断支援サービスの導入方法は?メリット・費用なども解説
健診に遠隔読影の利用が推奨される医療機関

下記のような医療機関は、健診に遠隔読影を利用することで大きなメリットを得られます。
一度に多数の検査を実施する
巡回健診バスを運用するような医療機関では、一度に多数の検査を実施するため、大量の検査データが短期間で発生します。通常、複数の患者の撮影を一度に行い、その翌日にまとめて読影依頼が発生します。
結果報告書を手書きの紙レポートで作成する地域もあるため、データ量が多いと迅速な読影が難しくなります。こうした状況に対応するため、医師会など周辺医療機関と協力して読影を分担し、効率的に対応する体制を整えることが一般的です。
遠隔読影を導入すれば、多量の読影も速やかに完了します。
二重読影によって診断精度を高めたい
二重読影は、同じ検査データを2人の専門医がそれぞれ独立して評価することで、診断精度を高める手法です。「ダブルチェック」とも呼ばれ、ヒューマンエラーを可能な限り排除しつつ、診断の確実性と迅速性を両立させるために利用されています。
二重読影には、オーバーリーディングとブラインドリーディングの2つの方式があります。オーバーリーディングでは、一次読影医の結果を基に別の医師が二次読影を行い、診断結果の確認や補足を行います。
一方でブラインドリーディングは、一次読影結果を伏せたまま、もう1人の医師が二次読影を行う方法です。他の医師の診断に影響されず客観的な評価が期待できます。遠隔読影では、どちらの方式にも対応可能 です。
人材確保が難しい地域にある
遠隔地や医療資源が限られている地域では、読影医の確保が極めて困難で、診断体制の維持が大きな課題となっています。遠隔読影を導入することで、高精度な画像診断が可能になり、地元の患者が迅速に専門的な診断を受けられるようになります。
さらに、遠隔読影を利用することで、限られた医療スタッフにかかる負担を軽減し、医療提供体制の安定化を図ることも可能です。特に、医療過疎地や高齢化が進む地域では、遠隔読影が地域全体の医療の質向上に寄与し、患者の安心感も高まるでしょう。
まとめ
遠隔画像診断支援サービスは、読影医不足の解消や、需要変動による負担軽減、さらには緊急時のバックアップとして役立ちます。
iMedicalの遠隔画像診断支援サービスは、4つの大学病院と連携し、優秀な読影医を確保するとともに、厳格なタレントマネジメントシステムを採用して品質管理を徹底しています。また、医療機関とのシステム連携によって迅速で効率的な画像診断体制を実現できます。まずはお気軽にご相談ください。
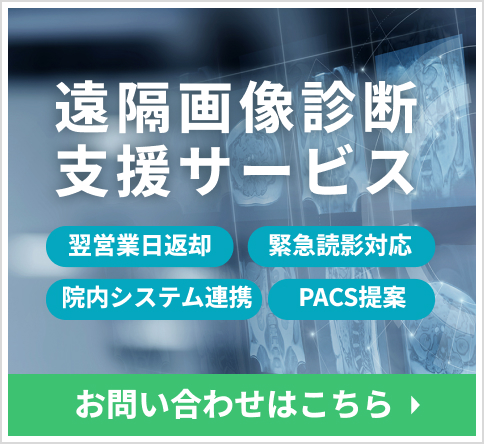

.png)
.png)