医療ICTとは?導入メリットと活用事例を分かりやすく解説

医療現場にもデジタル化の波が押し寄せています。特に注目されているのが「医療ICT」の導入です。電子カルテやオンライン診療、遠隔読影など、情報通信技術を活用した医療体制は、従来の医療の在り方を大きく変えつつあります。
本記事では、医療ICTとは何か、導入によるメリットや課題、具体的な活用事例について分かりやすく解説します。
医療ICTとは
医療ICTとは、医療分野において情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を活用し、診療・看護・事務業務などを効率化・高度化する取り組みを指します。具体的には、電子カルテやオンライン診療、遠隔画像診断、AIによる診断支援などが該当し、医療従事者間での情報共有や、患者とのコミュニケーションを円滑にすることが目的です。
医療ICTの導入は、診療の質の向上、医療現場の負担軽減、医療費の適正化にもつながるとされ、デジタル化の進展とともに今後ますます注目される分野です。
ITとの違い
IT(Information Technology)は、情報を処理・保存・管理するための技術全般を指します。これに対してICT(Information and Communication Technology)は、ITに「通信(Communication)」の要素を加えた概念です。
単に情報を扱うだけでなく、それを「誰かとつながるために活用する」という点がICTの特徴です。情報のやり取りを重視する医療現場では、ICTの考え方がより重視されます。
ICTとの違い
「医療ICT」と「ICT」は同じ技術基盤を指しますが、適用される領域が異なります。ICTは教育・行政・ビジネスなど幅広い分野に導入されていますが、医療ICTはその中でも医療分野に特化した活用を意味します。
医療ICTの現状
医療現場におけるICTの導入は、近年急速に進んでいます。電子カルテシステムとオーダリングシステムの普及率を例に、医療ICTの現状を紹介します。
令和5年時点で、一般病院における電子カルテシステムの導入率は65.6%に達しており、400床以上では93.7%と9割を超えています。200~399床では79.2%、200床未満でも59.0%と半数を超える水準です。一方、一般診療所での導入率は55.0%となっており、こちらも過半数に達しています。
オーダリングシステムにおいても、令和5年には一般病院全体の導入率が68.0%となり、400床以上では94.2%、200~399床で83.4%、200床未満でも61.2%となりました。
この結果から、医療ICTは一部の先進的な医療機関だけのものではなく、全国の多くの病院や診療所に広がりつつあることが分かります。中小規模の医療機関への導入拡大と、診療所レベルでの浸透が今後の課題といえるでしょう。
医療ICTを導入するメリット
医療現場におけるICTの導入は、医療の質を高めるだけでなく、患者や医療従事者、医療機関の運営面にも多くの恩恵をもたらします。以下では、医療ICT導入による代表的な5つのメリットを紹介します。
医療の質向上と業務効率化
ICTの導入により、医療現場では情報の記録・管理・共有がスムーズになり、診療の質と業務効率の両方が向上します。例えば、電子カルテを活用すれば紙の記録作業が不要となり、医師や看護師が本来のケア業務に集中しやすくなります。
また、検査結果や既往歴などの情報をすぐに検索・閲覧できるようになるため、判断の迅速化にも貢献できます。重複検査や記録ミスを減らすことにもつながり、診療の質が全体的に高まります。
患者の利便性向上
ICTによる業務効率化は、医療機関を訪れる患者にもメリットをもたらします。受付や診療の待ち時間が短縮されるほか、事前問診のオンライン化や予約管理システムによってスムーズな診療が可能になります。
さらに、オンライン診療や電子処方の活用により、自宅にいながら受診や薬の受け取りができる環境が整うため、通院が難しい患者にとって大きなメリットです。
医療スタッフの働き方改革
医療ICTは、医療従事者の業務負担を軽減し、働き方改革の推進にもつながります。例えば、電子カルテやオーダリングシステムによって、手作業による記録や指示のやり取りが効率化され、長時間労働の是正が期待できます。
また、在宅勤務が可能な事務作業の一部をリモートで対応できる体制を整えることで、多様な働き方の実現にも貢献します。医療従事者の離職防止や人材の確保にもつながる重要な施策といえるでしょう。
医療コストの削減
ICT化によるデジタル管理は、医療現場のコスト削減にも寄与します。紙カルテや検査依頼書の印刷コスト、人手による集計や管理の手間を削減できる上、診療データの活用によって無駄な検査・処方の回避にもつながります。
加えて、診療の質の向上や患者満足度の改善が、医療機関全体の経営効率を高める好循環を生む要因となります。
新薬や治療法の開発に役立つ
医療ICTが生み出す膨大な医療データは、創薬や新たな治療法の研究に活用される重要な資源です。電子カルテや検査データから得られる情報をAIで解析することで、疾患ごとの傾向や有効な治療パターンを見つけやすくなります。
また、ビッグデータをもとに薬効の予測や副作用リスクを事前に評価できるようになることで、研究開発にかかる時間とコストを大幅に削減できます。
医療ICTを導入する際の課題

医療ICTは多くのメリットをもたらす一方で、導入・運用にあたってはいくつかの課題があります。医療ICTを導入する際の課題について詳しく見ていきましょう。
教育体制や制度を整える必要がある
医療ICTの活用には、機器を使いこなせる人材の育成と、それを支える制度整備が不可欠です。現場のスタッフが新しいシステムを十分に理解・活用できなければ、せっかくのICTも効果を発揮しません。
特に高齢の医療従事者が中心となっている医療機関では、操作習得へのハードルが高く、導入後も業務が円滑に進まないケースがあります。また、電子カルテや診療支援システムの仕様が統一されていないため、医療機関間での連携が難しくなることも課題の一つです。
ICTを浸透させるためには、継続的な研修やマニュアル整備に加え、国や自治体による標準化や支援制度の整備が求められます。
セキュリティやプライバシーの対策が必要
電子カルテやクラウド診療支援システムの活用により、患者の個人情報がインターネットを介して管理される機会が増えています。そのため、サイバー攻撃やデータ漏えいへの対策は、医療ICT導入における最重要項目といえるでしょう。
対策としては、強固な認証システムの導入やアクセス権限の管理、定期的なシステム更新が基本となります。加えて、外部業者への委託時には情報管理体制の確認を行い、万が一の事態に備えたガイドラインや対応手順を整備しておくことが欠かせません。
患者の信頼を守るためにも、情報セキュリティに対する継続的な見直しと強化が必要です。
システムエラー時の対応が必要
ICTは利便性が高い反面、システム障害や通信トラブルが発生した際には、診療業務全体に大きな影響を及ぼすリスクがあります。電子カルテが一時的に使えなくなれば、診療の遅延や記録の混乱が生じ、医療事故の一因にもなりかねません。
そのため、導入時には必ずバックアップ体制を構築し、非常時のマニュアル対応が可能な運用ルールを定めておく必要があります。また、システム停止時のために一部紙ベースの運用を残すなど、冗長性のある設計が求められます。
注目される医療ICTの活用事例
医療ICTの導入が進む中で、実際に現場で活用されている代表的な事例にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、医療ICTの活用事例を紹介します。
電子カルテ・お薬手帳
電子カルテは、患者情報をデジタルで一元管理できるシステムで、紙カルテに比べて検索性や共有性に優れています。医師・看護師・薬剤師など複数の医療従事者がリアルタイムで情報を把握できるため、連携がスムーズになり、医療ミスの防止にもつながります。
電子お薬手帳は、服薬履歴をクラウド上で管理できるサービスで、患者自身もスマートフォンを通じて内容を確認できます。
このようなICTツールの活用は、患者と医療機関の双方にとって情報管理の利便性を高めています。
オンライン診療
オンライン診療は、患者が自宅などから医師の診察を受けられる新しい診療スタイルです。スマートフォンやパソコンを使って遠隔で診察が行えるため、通院が困難な患者にも対応しやすいのが特徴です。
医療機関にとっては、対面診療に比べて感染症リスクや待合室の混雑を軽減できるというメリットもあります。
オンライン診療の普及により、患者の利便性と医療現場の柔軟性がともに向上しています。
遠隔読影
遠隔読影とは、専門の読影医が、離れた医療機関で撮影された画像をもとに診断を行う仕組みです。地域によって読影医が不足している医療機関でも、遠隔読影を活用することで質の高い画像診断を受けることができます。
例えば、遠隔画像診断支援サービスでは、医療機関で撮影したCTやMRIの画像を、安全な通信ネットワークを通じて読影医に送信し、診断結果のレポートが迅速に返送されます。サービスによっては早ければ当日中に診断結果が届くケースもあり、治療の初動を大きく早めることが可能になります。
まとめ
医療ICTは、単なるIT化ではなく「医療の質と利便性を高める」ための基盤となる仕組みです。電子カルテの普及、オンライン診療の拡大、遠隔診断の活用など、現場では着実に活用が進んでいます。
一方で、教育体制の整備やセキュリティリスク、システム障害への備えなど、導入には慎重な準備と継続的な見直しが求められます。しかし、これらの課題を乗り越えてICTを活用できれば、患者・医療従事者・医療機関のすべてにとってメリットの大きい環境が実現するでしょう。
中でも遠隔画像診断支援サービスは、医療資源の地域格差や専門医不足の解消に大きく貢献する分野として注目されています。
「読影医が不足している」「装置の稼働率を高めたい」「専門医の意見を仰ぎたい」といった課題を感じている医療機関の方は、iMedicalの遠隔画像診断支援サービスの導入もご検討ください。
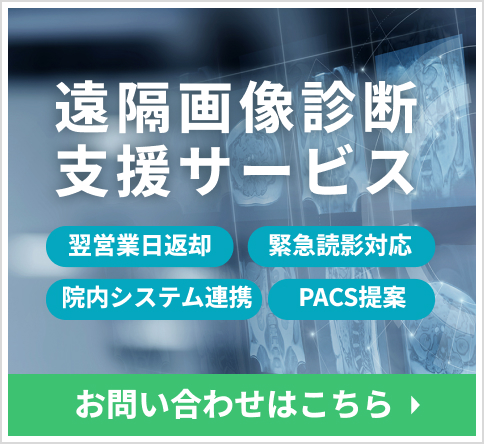

.png)
.png)